
先週のアメリカ大統領選では、ヘッジファンドの仕掛けなどにより相場が乱高下しました。
相場が暴落したところで、買うことができた方は、数日で大きな利益を得たことと思います。
とはいえ、暴落の真っ只中では、いつの場合も、途方もない恐怖心が蔓延し、たいていの方は買い向かうことはできないものです。
今回は、「買える暴落」と「買えない暴落」の基準について考えてみました。
今回のアメリカ大統領選挙や、6月のイギリスEU離脱の国民投票などは、管理人からみると、明らかに「買える暴落」でした。
相場が短時間で、急激に総悲観モードとなり、どこまで落ちるのか、この先どうなるのかという恐怖心に包まれますが、後でよくよく考えてみると、どちらのケースも、その後すぐに、世界経済が致命的な打撃を受けるような事象ではありません。
両ケースとも、数時間程度で日経平均が1000円以上下落していますが、この下落スピードも「買える暴落」か「買えない暴落」かを判定する材料であると考えます。
短時間で急激に下落する場合は、間違いなくヘッジファンドなどの売り仕掛けが入っており、いずれ利益確定のために買い戻す時が必ず来ます。
先週の暴落が、もし、1日で300円や500円程度の下落であったならば、売る人が多いけど、中には下を積極的に拾う人もいるという事ですから、一概に「買える暴落」とは言えない状況でした。
買えない暴落とは、例えば2008年のリーマンショックのようなケースです。
2008年9月15日に、アメリカの投資銀行であるリーマンブラザーズが破綻して、週明けである9月16日の日経平均は、前週終値12214.76円から、当日終値11609.72円まで605円下落しました。
リーマンブラザーズについては、負債総額が数十兆円に膨らんでいました。
もし破綻すると、世界中の金融機関で大幅な資産の評価損が生じ金融恐慌に陥ると言われておりましたので、破綻直前まで「大きすぎて潰せない」と世間で考えられており、最終的には他金融機関や米国財務省が救済するとみられていましたが、これが一転破綻となりました。
当時は、今ほどコンピューターによる自動売買システムが浸透していない時代でしたので、日経平均も600円程度の下落で済んでいますが、もし現在、同じような事象が起こったならば、恐らく数千円下落していたことでしょう。
日経平均は、その後も下落を続け、2008年10月18日に6994円まで、1カ月程度で5000円以上暴落する事態となりました。
リーマンショックの場合は、破綻により世界中の金融機関で実際に大きな損害が発生することがわかっており、9月16日の暴落は「買えない暴落」でした。
似た「買えない暴落」の例としては、1998年秋に発生したアメリカの大手ヘッジファンド「LTCM」の破綻などがあげられます。
「買える暴落」の特徴は以下と考えています。
・発生事象がその後の世界経済に及ぼす影響が見えていない漠然とした不安による暴落
・暴落幅が急激で、明らかに空売りの仕掛けであると判定できる暴落
・金融機関の大規模な損害など、実際の大金が絡む事象でない暴落
・その後の世界経済に大きな影響のない局地的な事象による暴落(大地震、局地戦争など)
一方、「買えない暴落」とは、リーマンショックのような実際に大きな損害がからむ暴落や、発生したことはありませんが、例えば核戦争勃発などの世界情勢を大きく変える事象にからむ暴落であると考えています。
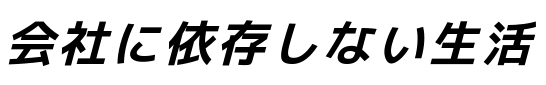

コメント